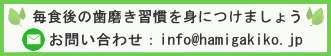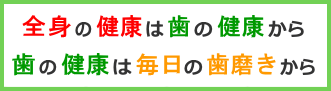歯科治療で注意するべき全身疾患dental treatment systemic disease
ホーム > 歯科治療で注意するべき全身疾患
高齢化率の上昇に伴って、全身疾患を患っている患者数も増え続けているのが現状です
日本の総人口は、
平成29(2017)年で1億2,671万人
となっています。
その中で65歳以上人口は、
3,515万人となり、
総人口に占める割合
(高齢化率)も27.7%となりました。
そして、
高齢化率の上昇に伴って
高血圧症や糖尿病などの
全身疾患に罹っている患者数も
増加しています。
当然、
歯科医院を受診される患者の中で
何らかの全身疾患を持っている割合も
増えてきます。
だからこそ、
歯科医師も様々な全身疾患に対して
正しい対応が求められるのです。
もちろん、
患者様もご自身の全身疾患が、
歯科治療時にどのようなリスクを与えるのか
知っておくことは、
とても大切であると言えます。
平成29(2017)年で1億2,671万人
となっています。
その中で65歳以上人口は、
3,515万人となり、
総人口に占める割合
(高齢化率)も27.7%となりました。
そして、
高齢化率の上昇に伴って
高血圧症や糖尿病などの
全身疾患に罹っている患者数も
増加しています。
当然、
歯科医院を受診される患者の中で
何らかの全身疾患を持っている割合も
増えてきます。
だからこそ、
歯科医師も様々な全身疾患に対して
正しい対応が求められるのです。
もちろん、
患者様もご自身の全身疾患が、
歯科治療時にどのようなリスクを与えるのか
知っておくことは、
とても大切であると言えます。
高血圧症と歯科治療
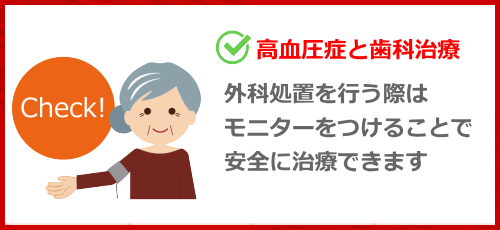
血圧がコントロールされている状態で歯科治療します
高血圧症の患者さんを治療する時は
モニターをつけるのが基本となります。
歯科治療を受けるときに、
治療への不安や治療時の疼痛などによって、
血圧が急上昇することがあり、
血圧の急激な上昇は
心血管病を悪化させるリスクが高いからです。
続きはこちらから。
高血圧症の患者さんを治療する時は
モニターをつけるのが基本となります。
歯科治療を受けるときに、
治療への不安や治療時の疼痛などによって、
血圧が急上昇することがあり、
血圧の急激な上昇は
心血管病を悪化させるリスクが高いからです。
続きはこちらから。
糖尿病と歯科治療
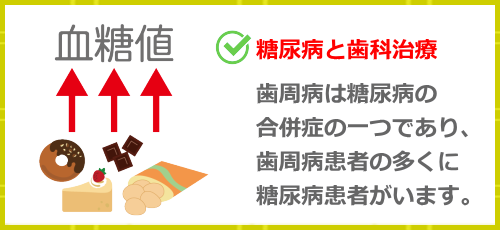
治療開始前に糖尿病の状態確認をしましょう
糖尿病患者は
代謝異常による感染防御機構の機能低下によって
易感染性であり感染の合併頻度が高いです。
そのため、治療開始前に患者さんが
まず糖尿病に罹っているかどうかを
確認することがとても大切です。
また、糖尿病に罹患している場合は、
かかりつけ医に対診をとって
治療内容やコントロール状態を
正確に把握する必要があります。
続きはこちらから。
糖尿病患者は
代謝異常による感染防御機構の機能低下によって
易感染性であり感染の合併頻度が高いです。
そのため、治療開始前に患者さんが
まず糖尿病に罹っているかどうかを
確認することがとても大切です。
また、糖尿病に罹患している場合は、
かかりつけ医に対診をとって
治療内容やコントロール状態を
正確に把握する必要があります。
続きはこちらから。
慢性肝炎と歯科治療
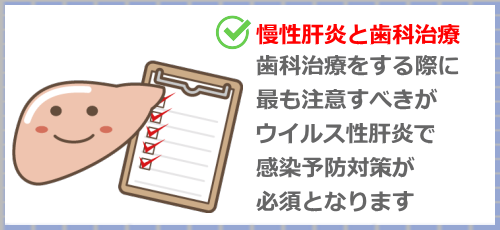
ウイルス性肝炎では感染予防対策が必要です
治療をする際に最も注意すべきが
ウイルス性肝炎で、
C・B型肝炎ウイルスは血液から感染するので、
歯科従事者だけでなく
歯科診療行為によって
他の患者へ感染さえる可能性もあります。
使用した器具の取り扱い・消毒は徹底させるべきです。
続きはこちらから。
治療をする際に最も注意すべきが
ウイルス性肝炎で、
C・B型肝炎ウイルスは血液から感染するので、
歯科従事者だけでなく
歯科診療行為によって
他の患者へ感染さえる可能性もあります。
使用した器具の取り扱い・消毒は徹底させるべきです。
続きはこちらから。
誤嚥性肺炎と歯科治療
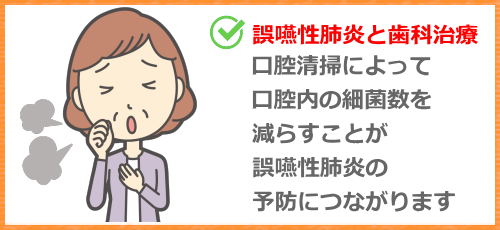
誤嚥性肺炎の原因として口腔細菌が挙げられます
歯周病の原因菌であるグラム陰性菌が
誤嚥性肺炎の原因となることが多く、
唾液分泌量の低下等によって
口腔内のグラム陰性菌が増えて
口腔から咽頭、気道内に入っていくことがあります。
誤嚥性肺炎を予防する意味でも、
的確な口腔清掃によって
口腔内にいる細菌数を減らすことが大切となります。
続きはこちらから。
歯周病の原因菌であるグラム陰性菌が
誤嚥性肺炎の原因となることが多く、
唾液分泌量の低下等によって
口腔内のグラム陰性菌が増えて
口腔から咽頭、気道内に入っていくことがあります。
誤嚥性肺炎を予防する意味でも、
的確な口腔清掃によって
口腔内にいる細菌数を減らすことが大切となります。
続きはこちらから。
慢性腎不全と歯科治療
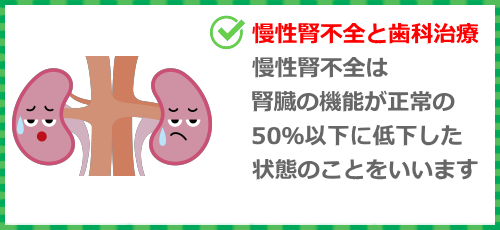
慢性腎不全は腎不全による非可逆性の腎障害です
血液透析患者は
循環器系の疾患を合併していることが多いです。
そのため、治療中のモニタリングが有効です。
なお、モニタリング時は
圧迫によってシャント等が閉塞するのを
予防するために、
バスキュラーアクセスの位置を確認して、
シャントがある方の腕で
血圧測定を決して行わないようにしましょう。
シャント等の位置については
透析主治医への対診で確認するようにします。
続きはこちらから。
血液透析患者は
循環器系の疾患を合併していることが多いです。
そのため、治療中のモニタリングが有効です。
なお、モニタリング時は
圧迫によってシャント等が閉塞するのを
予防するために、
バスキュラーアクセスの位置を確認して、
シャントがある方の腕で
血圧測定を決して行わないようにしましょう。
シャント等の位置については
透析主治医への対診で確認するようにします。
続きはこちらから。
歯科治療で注意すべき骨粗鬆症治療薬まとめ
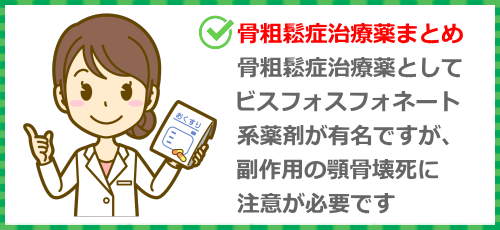
副作用の顎骨壊死に注意です
ビスフォスフォネート系薬剤の使用経験がある患者が、
抜歯などの顎骨に刺激が加わる治療を受けた時に、
副作用として顎骨壊死が発生する可能性があります。
また、骨転移治療薬としては
BP系薬剤だけでなくデノスマブ(ランマーク)も
利用されていますが、
副作用として顎骨壊死が報告されています。
続きはこちらから。
ビスフォスフォネート系薬剤の使用経験がある患者が、
抜歯などの顎骨に刺激が加わる治療を受けた時に、
副作用として顎骨壊死が発生する可能性があります。
また、骨転移治療薬としては
BP系薬剤だけでなくデノスマブ(ランマーク)も
利用されていますが、
副作用として顎骨壊死が報告されています。
続きはこちらから。